|
|
|
|
|
|
|
|
土間
|
|
|
|
土間は外の表情を持つマルチ機能空間になります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

土間で魚を焼く
|
|
|
|
住宅プランの中での土間の役割(空間機能)
狭い玄関や廊下をつくらず、その分のスペースで
広い土間をつくると快適です。
生活を楽しむ場。
・好きなものを飾ったり、趣味の作業をする場。
・雨の日などは傘を広げて干したりできる実用空間。
・玄関が家族の趣味を演出する展示室になります。
土足で歩ける土間のもう一つの機能は縁側として
の役割です。最近の家では見かけなくなりましたが
立ち寄った人が靴を脱がずに気軽に腰掛けて話がで
きる場です。家にあがると気を使いますが,土間だと
気も楽で話も弾みます。近所の方と程よい距離を持
ちながら良い関係をつくる場になります。
|
 |
|
|
|
土の土間(三和土)

土の土間は地面をそのままのこせばいいわけでなく、適切な造り方が必要です。
|
|
|
|
昔の農家にあった土間と同じつくりです。
土間の下は土の地面です。適度な湿気は必要です、
土の土間の下はコンクリートにはしないほうがよい。
一般的な住宅で行う布基礎方式の場合は必然的に
30~35cmのレベル差なります。腰かけにちょうど
良い高さです。
土間の厚さは10cmが目安です。
土の酸性度を下ること,無菌状態にすること,ヒビの
でない土間にすることがポイントです。
1. 土の上に石灰をまいて土を弱アルカリ性にする。
(菌を殺してカビを出さないため)石灰をつかう。
(コンニャクをつくるのと同じ消石灰です。)
2. 土(粘土質)に川砂、石灰(消石灰)をまぜる。
瓦をつくる粘土と同じ山中の5,6m下の無菌の土
をつかう(粘土は酸性)
粘土と石灰を混る時水分が足りない場合ニガリを
少しまぜることもある。)
粘土に石灰を混ぜ水を加えると水和反応で土粒子
が結びつき、硬さが発生する。
石灰(水酸化カルシウム)が空気中の二酸化酸素と
時間をかけて反応し、硬さを増してゆく。
3.砂をまき、転圧してゆく。2段重ねで施工する。
転圧し真空状態にする。ヒビを出さないため。
(土の粒子を密着させ、強度をあげる。)
足で踏み固めると同時に、木槌でたたく。
4.石灰をまいて更に転圧し表面に砂をまいておく。
(ヒビが出ても砂が入り込んでわからなくなる)
|
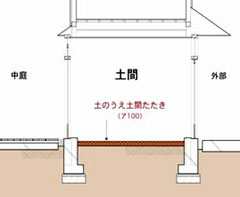
→ 雑誌「木の家に暮らす」
→ 新聞紹介
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
タイル/木の土間
|
|
|
|
より内部空間に近づけた仕上が適当な場合
床材にタイルや木材を使用します。
清掃がしやすく清潔です。

木の床
廃材などを利用すると味がある。 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土壁
|
|
|
|
本格的な土壁をつくりませんか。
下塗り状態のままでも風格のある仕上が得ら
れます。昔の農家で見かけた荒っぽい土壁
ですが、細かなヒビ割れが美しい。
コストは心配するほどではありません。
珪藻土ばかりが土壁ではありません。
|

下塗りのままで仕上げた土壁
|
|
|
|
土壁づくり
|
|
|
|
荒木田土(地元の土)とよくからませた土をつかい、更にたたい
て柔らかくしたワラをまぜて、3日間程度ねかせてた土をつかう。
上質の粘土(荒木田土)に2~3寸の切り藁を練り込み3~6ヶ月
間水分を保って寝かし藁を自然発酵分解させた土をつかいます。
専用の土も市販されています。
 |
|
 |
|
ヒビが発生する。
どういうヒビがでるかわか
らないのがおもしろい。
|
現場ぬり付け直後
|
|
2週間後ヒビがでる
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
木コテでワラをたたいて混ぜる
|
|
よくワラと土を撹拌する
|
|
2~3日ねかせて使用する
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
縁側
|
|
|
|
縁側を復活させましょう。
 |
|
 |
板敷きの縁側
→ 住宅紹介 |
|
廃材を再利用したデッキ状のテラス
|
|
|
|
|
|
|
|
→ 戻る
|
|


